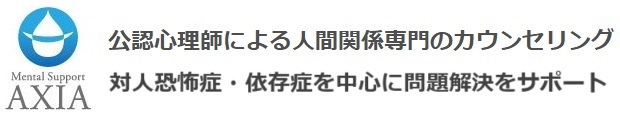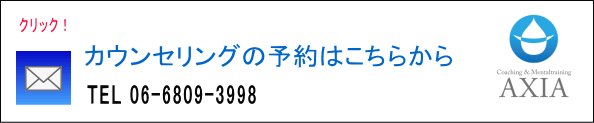相手の気持ちを考えることができないところを指摘されて変えなければと思っている人、人の気持ちがわからない相手との関係で苦しんでいる人に役立つ内容をお伝えしていきます。
相手の気持ちを考えることができないのはなぜ?
自分のことばかり考えている
人間関係で悩んでいる人は、一日のほとんどの時間を「自分が相手からどう思われているか」を考えることに費やしています。
そして、何か失敗したと思う出来事があれば終わった後でもクヨクヨ考えて悩み続ける。
自分のことばかり考える状態になっている以上、相手の気持ちを考える余裕なんてありません。
一般的に自己中と呼ばれる自分の欲求を満たすことばかり考えている人も同じです。
一人の世界に入り込む時間が長ければ長いほど他者とのかかわりがなくなり、結果として人の気持ちを考える機会が失われます。
自分のことばかり考えているから相手の気持ちを考えることができない状態になっているのです。
感情を抑圧している
自分の感情を抑え込んでいると相手の気持ちを考えることができない状態になります。
相手の気持ちがわかるというのは、相手の気持ちに共感できているということです。
自分の感情を抑圧している人は、自分の感情を感じ取ることができず、その結果、他人の感情を感じ取ることもできない状態になっています。
例えば、「仕事がつらくてもう辞めたい」という愚痴を聞いたとして、「仕方がない」「やめればいい」と安易に言えるのは共感できていないからです。
ニュースを見ても感情移入することがほとんどなく、ただ情報として受け取るだけになっている人は感情を抑圧している可能性が高いでしょう。
自分が我慢して丸く収まるならいいと思っていませんか?感情の抑圧は自覚がないまま大きな問題を引き起こしています。
主観が強い
以前参加した交流会で主催者を胴上げするというサプライズ企画がありました。
司会の方が「胴上げしたい方は前に出てきてください」とアナウンスされたので、胴上げしたい人たちが前に集まって行ったのです。
そのとき、私の隣にいた方が「参加しないんですか?」と聞いてこられた為、「いえ、まともに話したこともないので…」と答えたところ、「そんなこと気にしなくていいのに」と言われ「?」になりました。
たぶん隣の方は私が遠慮していると思ったのでしょう。
しかし、私は遠慮したわけではなく、単に胴上げしたいと思わなかっただけでした。
主観が強ければ強いほど相手の気持ちを考えることができなくなってしまうところがあるのです。
発達障害の傾向がある
発達障害の影響で相手の気持ちを考えることができないのかもしれません。
発達障害の一つである「自閉症スペクトラム症(ASD)」は想像力の欠如を抱えています。
相手が社交辞令で「また機会があれば飲みに行きましょう」と言ったとして、発言の意図、背景を想像できれば社交辞令か本心かをある程度は判別できる。
しかし、想像できなかった場合は社交辞令でもそのまま受け取って「いつ飲みに行くのですか?」と聞いてしまったりする。
自閉症スペクトラム症と診断されていない人でも、想像力が乏しい人、相手の意図を考える習慣がない人は同じような状態になってしまう可能性があります。
発達障害について。当事者である私自身の体験を踏まえて自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)を中心に説明しています。
相手の気持ちを『考えること』と『感じ取ること』
相手の気持ちを考えることができない人は、相手の気持ちを感じ取ることができていません。
小さい頃から「相手の気持ちを考えなさい」と言われて育ってきた人が多いと思いますので、「相手の気持ちを感じ取る」という表現は聞きなれないのではないでしょうか?
例えば、友達が怪我をして血を流している姿を見たときに「痛そう」と思うのは相手の痛みを感じ取っていることになります。まるで自分が怪我したかのように相手の痛みを感じ取るから早く手当てしないととなるのです。
もし、相手の気持ちを考えただけの場合どうなるでしょう?
血を流している姿を見て「血が出るくらいだから痛いだろうな」と考えます。そして、血が出ているからまずは血を止めることが必要だと判断して手当てをする感じになりますかね。医者や看護師のような対応でしょうか。
どちらも最終的に手当てはしますし、考えるほうが適切な判断になりやすい傾向はあります。
ただ、その態度を見た相手はどう思うでしょうか?
自分の痛みを感じ取って心配そうに焦って手当てしてくれるのと、心配していないことはなくともどこか冷静に手当てされるのとでは受け取り方がまったく違ってきます。
つまり、人は相手の気持ちを感じ取っている人に対して、自分のことを本当に考えてくれていると思うのです。
相手の気持ちを感じ取ることができていない以上、どれだけ頑張っても相手の気持ちを考えることはできないんですよね。
相手の気持ちを考えることができない状態を改善する取り組み
自分の気持ちを感じ取れるようになる
相手の気持ちを考えることは意識すればできますが、感じることは意識しようとしてもどう意識していいかわかりませんよね。
相手の気持ちを感じるためにはまず自分の気持ちを感じ取ることが必要になります。
自分の気持ちを感じ取れない鈍感な人は相手の気持ちにも鈍感。逆に、自分の気持ちを感じ取れる敏感な人は相手の気持ちにも敏感。
人は自分が感じたことのある気持ちの範囲でしか相手の気持ちを感じることができないため、自分の気持ちを感じ取れるようにならない限り相手の気持ちを感じ取ることができないのです。
自分の気持ちに敏感になるためには、まず日々自分の気持ちに目を向けて「どういう気持ちだったのか?」「どう感じたのか?」を意識する習慣を付けていきます。
ただ、自分の気持ちに鈍感な人は無意識に自分の気持ちを見ないようにしてきた部分がありますので、カウンセリングで少しずつでも自分の気持ちを話していくことが必要です。
自分で話していくだけで気付けることもありますし、カウンセラーからの質問で気付くことも出てきます。
「本当はこんな気持ちだったんだ」という気付きが増えていくことで今まで見えなかった自分の気持ちが見えてきて、どんどん自分の気持ちを感じ取りやすくなり、結果として相手の気持ちも感じ取れるようになっていくのです。
相手の気持ちを感じ取れるようになるのは簡単ではありませんが、日々自分の気持ちと向き合うこと、相手の気持ちを感じ取ろうと意識することを諦めずに継続していけば少しずつできるようになっていきます。
客観視する力を高める
誰しも主観の中で生きているものですが、主観が強い人ほど相手の意図をゆがめて認識しやすくなります。
主観が強くなりすぎると相手がやっていないことまでやったと認識することだってありえますからね。
また、人に好かれやすくなる要素の一つである「相手の話を素直に聞く」という観点からしても主観は強すぎない方がいいと言えます。
「相手がこういう話をしたからこう思ってるはずだ」「相手がこういう態度だからこう思ってるに違いない」等と決め付けてしまいやすいと思いますが、一度本当にそうなのか相手に聞いてみるようにしてみて下さい。
素っ気ない返事だから機嫌が悪いと思ったけど実際は違っていたということが数多く出てくるはずです。
本人に聞きづらければ、相手のことを知っている別の人に聞いてみるでもかまいません。
自分の主観に気付いて客観視する力を養うことにつながっていきます。
客観的に見ることができればできるほど自分の主観にとらわれず相手の目線で見ることができるようになるのです。
どうすれば自分を客観視できるようになるのかを具体的にお伝えしています。
相互通行のコミュニケーションを心がける
相手の気持ちを考えることができない人は一方通行のコミュニケーションを取っています。
相互通行のコミュニケーションに切り替えていくことが必要なのですが、どういうものかわからないと思いますので、まず以下の事例をもとにイメージすることから始めてください。
Aさんが必要のない作業に苦しむBさんを見かねて、「別にその作業はやらなくていいのではないか」と指摘するシチュエーションです。
一方通行のコミュニケーション
Aさん:「その作業大変じゃないですか?」
Bさん:「そうですね、でもやらないといけないんで…これがなかったら仕事だいぶ楽になるんですけどね」
Aさん:「じゃあ、やめたらいいんじゃないですか?実はすごく大変そうだなって思って見てたんですよ」
Bさん:「大変なんですけど、今までずっとやってきたことなんで簡単には変えれないんですよね」
Aさん:「Bさん、仕事で大切なことって何かわかります?」
Bさん:「えっ?う~ん…何でしょう…」
Aさん:「仕事っていうのはいかに効率よくするか、そして日々改善していくことが大切なんですよ。変えることを恐れていたら仕事なんてできないですよ」
Bさん:「でも、いきなり変えてミスが起こったらどうするんですか?」
Aさん:「変えたら絶対にミスが起こるって言えます?」
Bさん:「いえ、絶対ではないと思います」
Aさん:「とりあえずやってみましょうよ。やってみてどうかだと思うんです」
Bさん:「はぁ…」
相互通行のコミュニケーション
Aさん:「その作業大変じゃないですか?」
Bさん:「そうですね、でもやらないといけないんで…これがなかったら仕事だいぶ楽になるんですけどね」
Aさん:「そうですか…難しいですね。ちなみにこの作業って何のためにされてるんですか?」
Bさん:「う~ん、前任者からの引継ぎでこうするようにと言われたので何のためにって聞かれると困ります」
Aさん:「引継ぎで言われたからされているんですね。昔からこのやり方なんでしょうかね」
Bさん:「どうでしょう。その辺は全然わからないです」
Aさん:「ですよね…他の方ってこの作業のこと知ってるんですか?」
Bさん:「いえ、私しかやってないので誰も知らないです」
Aさん:「Cさん(上司)も知らないんですか?」
Bさん:「はい、細かい仕事の進め方は任されてますので」
Aさん:「それでもこの作業を続けてる意味って何かあるんでしょうかね」
Bさん:「いえ、別に意味はないんですけどね…」
Aさん:「そうですか…そういえば、私が前にいた職場でも同じようなケースがあって今までのやり方変えてミスが起こったりするのを気にされてたんですけど、そういうのもないですか?」
Bさん:「たしかにミスは恐いですね。それはあると思います」
Aさん:「そもそも、この作業って何かの役には立ってるんですかね?」
Bさん:「いえ、とくに何の役にも立ってないです…よく考えてみるとこれ意味ないですね(笑)」
Aさん:「ですね(笑)」
Bさん:「今まで考えずにやってましたけど、面倒くさいだけなのでやめましょうか」
一方通行と相互通行の違い
一方通行の場合はすでに自分の中で答えが決まっていて相手を誘導する形になっています。
それに対して、相互通行の場合は一緒に答えを探していく形になっているのが大きな違いです。
相手の表面的な言動や行動だけを見て自分の基準でジャッジするのが一方通行のコミュニケーション。
相手の言動や行動の背景を想像しながら一緒に考えていくのが相互通行のコミュニケーション。
知ったからといってすぐ実践できるものではありませんが、なるべく相互通行のコミュニケーションを取ろうと心がけてください。
カウンセリングでは具体的なレクチャーをおこない、相手の気持ちを考えることができない状態を改善に向けていきます。