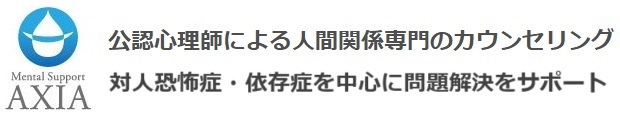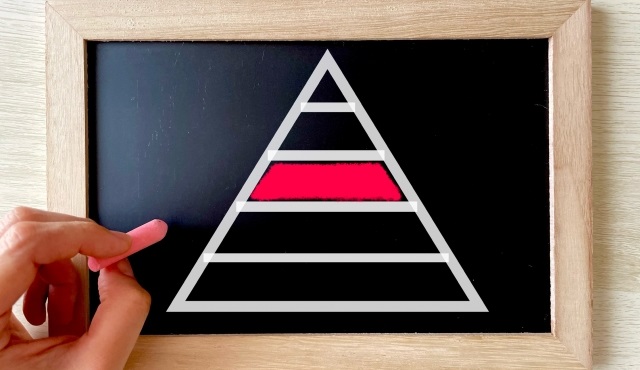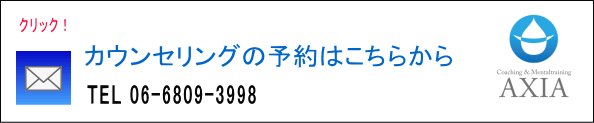私自身、今は親の接し方や家庭環境の影響が大きかったと思っていますが、以前は認めたくありませんでした。
幼少期から「お兄ちゃん」という役割のもと我慢を強いられ、毎日のように繰り広げられる夫婦喧嘩に怯えながらタコができるまで指を吸ったりボロボロになるまで爪を噛んだりして何とか寂しさを紛らわせた日々。
いまだにストレスが溜まると過呼吸を起こすのは母親に逆らったことがキッカケです。
それでも、「過去のことなんて関係ないだろ」と思っていました。
今起こっている問題にわざわざ過去を出してくることが気に食わなかった。というか、納得がいかなかったのです。
過去を掘り返すカウンセリングに強い反発を抱き、過去に触れずに改善できる方法がないのかと模索した時期もありました。
しかし、カウンセリングを重ねれば重ねるほど過去の親子関係の影響が大きいことに気付き、関連性を考えるようになったのです。
子供の性格形成に親の影響はほとんどない?
近年の遺伝学や発達心理学において、親の接し方や家庭環境による子供の性格への影響はほとんどないと言われています。
遺伝子の影響が50%前後で残りが環境要因。
環境要因だから「やっぱり家庭環境の影響があるのでは?」と思うのですが、実はこの環境というのは学校等の非共有環境を指しています。
こうした遺伝子の違いがどのくらい一人ひとりの性格の違いを説明するかをふたごのデータから算出すると,だいたい50%前後になります。これは残り50%が環境によることを意味します。しかし親の影響や家庭の影響(これを共有環境といいます)は先にも述べたようにほとんどみられません。むしろ一卵性のふたごですら違う一人ひとりに独自な非共有環境が重要なのです。
イギリスの富裕層の男子は8才から10年間全寮制の寄宿学校で過ごし親とほとんど会わない。
それでも立派に育つのだから親ではなく仲間集団の影響が大きいんだという話もあります。
実は、子どもの性格に決定的な影響を及ぼすのは、親ではない。重要なのは仲間集団だ。家庭から解き放たれた子どもは仲間集団とのかかわり合いの中で、社会のルールや自らのキャラクターを身に付けていく。
性格学から考えても遺伝子の影響が大きいのは間違いないでしょう。
しかし、親の接し方や家庭環境の影響がほとんどないというのは言い過ぎではないかと思っています。
子供には親の影響を受けやすいタイプと受けにくいタイプがいるからです。
同じ兄弟でも親に従順で周りに流されやすい子と、親の言うことを聞かず自分の道を突き進む子とわかれますよね。
前者の場合は親の影響を受けやすいので、影響を受けたうえで家族以外の集団とかかわるようになっていく。
つまり、子供のタイプによっては親子関係が残りの50%に影響を及ぼすほど大きなものになる可能性があるわけです。
親子関係が子供に及ぼす影響が大きいと言わざるをえない理由
コミュニケーションの原点が親子関係であること
母親が子供を産んでそのまま育てたとすれば最初にコミュニケーションを取る相手は母親になります。
そこから、父親、兄弟姉妹、祖父母、親戚と広がっていきます。
生まれてすぐは自分で何もできないので泣いたり笑ったり態度に出して親にやってもらうという非言語コミュニケーション。
言葉がしゃべれるようになってからは態度だけでなく、わがままを言ったり、興味関心のあることを話したり、わからないことを聞いてみたりといったコミュニケーションが加わります。
たいてい子供とかかわる時間が長いのは親になりますので、親とのかかわりがコミュニケーションの原点となるのです。
例えば、母親が一方的に自分の考えを押し付けるコミュニケーションを取っていた場合、子供は自分の意見を言わず我慢するようになる。
習慣化されることによってその後の人間関係においても我慢を繰り返してしまうわけです。
過干渉とは何なのか?原因から子供に生じる問題、改善方法までお伝えしています。
親がいないと生きていけない時期がある
虐待をするような親、自分のことを否定してくる親、不安定で頼れない親…
どんな親であったとしても子供は一定の年齢まではその親のもとで生きていくしかありません。
親に見離されたら生きていけないわけです。
だから、無理やりでも合わせてやっていくしかない。
親の期待に応えて手がかからない良い子になるのも、生きていくために仕方がないことだったりします。
言いたいことがあっても「どうせ聞いてくれないし」と諦めたり、納得できないのに「自分のためを思ってのことだ」と正当化したり…
繰り返していく中でどんどん自分が空洞化して不安が増していく。
そして、何かのキッカケで心の病や問題行動が出てくることになるのです。
一般との感覚のズレが生じる
視野が狭い幼少期、それ以降も他の家庭を知らないとなれば、自分の家族がおかしかったとしてもそれが当たり前になります。
バラエティ番組は害があるからとNHKしか観ない、父親の言うことが絶対で逆らってはいけないとか。
その当たり前が学校等のコミュニティとズレていればいるほど、周りの人とのコミュニケーションがとりづらくなります。
どこに行くにもついて行って母親を先頭に歩くのは、当時の私たち家族にとって当たり前のことでした。
しかし、ある日その光景を見た親戚の人から「カルガモ一家」と言われたのです。
「カルガモって何やねん!」と思いつつ、中学生にもなっていつも親と一緒のところを見られて恥ずかしかった記憶が残っています。
私達家族からすれば当たり前のことでしたが、他人から見れば違和感を抱く光景だったということです。
「普通になりたい」と思うとき「普通ではない」という前提があります。自分が普通ではなくどこかおかしい気がするから普通になりたいと思うわけです。
反面教師によって自分の性質を否定する
親を慕っていたり尊敬していたりする場合に影響を受けるのは当然ですが、逆の影響も大きいと感じています。
些細なことですぐ怒り出す親を見て嫌な思いをし続けていると、同じようになりたくないと思って怒りを表に出さなくなる。
親子なので似通ったところはあるのですが、親を反面教師にしているとその部分が認められなくなってしまうのです。
私の場合、母親が怒るのがすごく怖かったので、怒りの感情を出さないように抑圧していました。
また、父親の子供っぽいところを馬鹿にしていたため、自分の子供っぽいところを見せないようにしていました。
本当は母親に似て頑固で感情的になりやすく、父親に似て子供っぽいんですけどね。
幼少期の人付き合いが親のコミュニティ内になる
幼稚園(保育園)、小学校、中学校と進んで行く中で少しずつ外の人とのかかわりが増え、自分で選んだ人とコミュニケーションが取れるようになっていきます。
しかし、幼少期はどうしても親のコミュニティの範囲でしか人とかかわることができません。
親が社交的であれば幅広い人付き合いができますが、特定の人としか付き合わなかったり、人付き合いをほとんどしないタイプであれば経験が積めなくなってしまうわけです。
私に似て非社交的で人見知りがひどかった娘が、社交的な妻に連れられて人とのかかわりを経験した影響で誰とでも話せるようになった事例があります。
人間の性格は習慣によって形成されているものばかりであるため、親がどういう習慣形成につながる生活をしているかによって子供のコミュニケーションが変わってくるわけです。
愛情のすれ違いが生じる
親としては愛情を注いできたつもり。なのに、子供は愛されたという実感が薄い、もしくはない。
親が学歴で苦労したから子供には苦労させまいという思いで無理やり塾に通わせたとします。
子供は勉強よりも友達と遊んだり、部活を楽しんだりしたかった。
でも、親は理解してくれず勉強しろと言うばかり。
親は自分の気持ちを受け止めてくれない、わかってくれない。
ここですれ違いが起きるわけです。
日本には察する文化のようなものがありますので、とくに家族間では言葉で伝えないことが増えてしまいます。
すれ違いがあっても言葉で伝え合うことがあれば解消できるはずなんですけどね。
幼少期に抱えた愛着の問題はその後の人生に大きな影響を与え続けるものです。 愛着障害の分類、愛着スタイル、克服方法とカウンセリングについてお伝えしています。
心の穴が形成される
どれだけ理想的な子育てができたとしても、子供には心の穴が形成されます。
カウンセラーのように子供の話にしっかり耳を傾けて、コミュニケーションを取っている親がいたとします。
素晴らしいコミュニケーションではありますが、反面そういう接し方をされた子供は他の人にも同じようなコミュニケーションを求める気持ちがどこかしら出てきます。
また、親が話を聞いてくれない家庭で育った人の気持ちが本当の意味で理解できなくなるというのもありますね。
親子関係で形成された心の穴が良くも悪くも子供の人生に影響を及ぼし続けるわけです。
私は親の影響で心の問題を抱えた結果、学生時代は大変な思いをするばかりだったのですが、悩んだことで人の心理に興味を持つようになって今は心理カウンセラーの仕事をしています。
親子関係について私が思うこと
親子関係の影響が大きいと書き連ねましたが、だからといって完璧な子育ては無理だと思っています。
子供の考えを尊重しなきゃと思いながらも子供の将来を思うと心配で親の考えを押し付けてしまったり。
失敗してもいいから任せようと思ってもどうしても代わりにやってしまったり。
ダメだとわかりながらも感情的になって怒鳴ってしまうこともあるでしょう。
意図的に子供を苦しめるようなことは絶対にあってはならないですが、結果的に子供を苦しめてしまうことは防ぎようがないと思っています。
子供も子供で親の未熟な態度から学ぶことがあるので、もしかすると必要なことなのかもしれません。
形として子供が生まれた時点で親になりますが、子供を育てながら自分自身も育てられて少しずつ親になっていくものだと思っています。
理想的な子育てより大事なこと
育児本を読み漁り、インターネットやSNSで情報を集め、育児関連のテレビや動画を見る。
子供の為を思うがこその行動かもしれませんが、いろんな情報を集めて理想的な子育てをするよりも大事なことがあります。
それは親が子供と一緒に楽しむことです。
離乳食は手作りが良いからと必死に頑張って疲れ果てている親を見て子供はどう思うでしょうか。
物心がついていない時期であっても、子供は親の気持ちを敏感に感じ取っています。
子供の為を思うのであればまず親が少しでも楽にいられる状態を目指すことが大切です。
親が子供に与える影響が大きいから頑張らないといけないではなく、「無理しすぎない範囲で今の自分にできることをやっていこう」と考えていただくといいのかなと思っています。