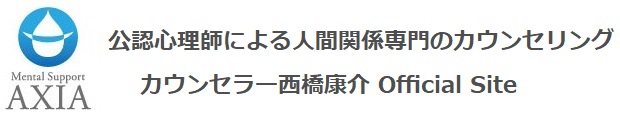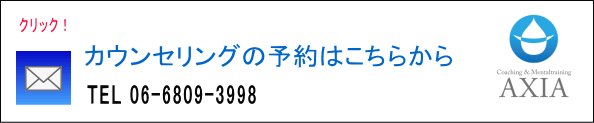コミュニケーションが上手く取れず不安を抱えている人は「コミュ障」と呼ばれることが多いです。
コミュ障は「コミュニケーション障害」の略語ですが、本来の医学用語としての意味とは異なり、人とのかかわりで支障をきたしやすい特徴を持った人を表す言葉として使われています。
ちょっと会話が苦手くらいの軽い意味で使われることもあれば、発達障害や対人恐怖症を抱えるほど深刻な人に対して使われることもある。 後者の場合は簡単ではありませんが、カウンセリングで改善していくことができます。
コミュニケーションへの苦手意識、不安について
「コミュ障」と呼ばれる人の特徴
- 会話が続かない
- 空気が読めない
- 傷つきやすい
- 自意識過剰
- 臨機応変な対応ができない
- 受け身で自分から話さない
- ネガティブ
- 一人の時間を好む
- 自信がない
コミュニケーションが上手く取れない原因
発達障害やHSPなど、生まれ持った性質の影響。「面白くない」と言われたりして傷ついた経験も影響します。
友達がいない、恋愛経験がない、学校や職場での孤立などコミュニケーションが取れないことで起こる問題が劣等感を生み出し、本当の自分をさらけ出せなくなっていく。
自分のことを隠しながら人とかかわることで、ものすごくコミュニケーションが取りづらくなっている面もあります。
日本人が潜在的に抱えている集団から排除されることへの恐れが影響して「普通ではない自分」「他人とは違う自分」が出せなくなってしまうのです。
また、高度成長期から核家族化が進み、電話、メール、LINE、SNSと対面せず人とかかわる機会が増え、コミュニケーションが複雑化してきたことも背景にあると思います。
カウンセリングでコミュニケーションの不安を解消していくために
何が問題なのかを把握する
コミュニケーションに不安がある、コミュニケーションが苦手というのは漠然としています。
まず「何が不安なのか?何が苦手なのか?」を実際の事例に基づきカウンセリングで知っていくことが必要です。
コミュニケーション能力に固執して本当の問題が見えなくなっているため、コミュニケーション以外のことに焦点が当たるように視野を広げていくアプローチもおこないます。
感情、思考、語彙力、表現力、コミュニケーションの取り方、自己肯定感、生まれ持った性質、固定観念、生活習慣…どこに問題があるかがわかれば、おのずとやるべきことが見えてくるのです。
問題を解決するための行動を取る
やるべきことが見えてきたら次は解決に向けて行動を起こす段階です。
カウンセリングでは専門的な知識とコミュニケーションの改善事例をもとに具体的な改善策を提示します。
一人で取り組めることを中心に、実際に人とのかかわりでもチャレンジしていく。トライアンドエラーで一緒に考えながら解決を目指す形になります。
自分だけでは気付けないことも多いため、カウンセラーから客観的な意見をもらうことも大切です。
問題が解決すればするほどコミュニケーションの不安は解消されていきます。
より良いコミュニケーションを目指す
コミュニケーションの問題が解決でき、コミュ障と言われなくなった時点で終了と思われるかもしれません。
しかし、それはあくまでもスタートラインでしかなく、マイナスがゼロになっただけの話です。
人とのかかわりにおいてゼロのままではいずれまた同じようにコミュニケーションで悩むことになります。
カウンセリングでは、より良いコミュニケーションで人との関係にプラスを生み出せる状態にします。
生きていく以上人とのかかわり、コミュニケーションに終わりはありませんので、成長し続けられる状態になることをゴールとしているのです。
コミュニケーション能力が高い「聞き上手」を目指す
ご存知の通りコミュニケーション能力は採用選考基準の一位となるくらいビジネスで重要視されています。
当然ながら評価や昇進にも密接にかかわっていて、仕事のスキルが高くなくともコミュニケーションが上手く取れれば評価されるという仕組みです。
コミュニケーション能力が高い人と言えば、「しゃべりが上手い人」「面白い話ができる人」「話題が豊富な人」というイメージではないでしょうか。
しかし、本当にコミュニケーション能力が高い人は話を聞く力を持っています。
明石家さんまさん、タモリさんといった話し上手と言われる芸能人の方を思い出してください。
相手の話をしっかり聞くことで意図を上手く汲み取って、それを話題として広げることで上手く話していますよね。
コミュニケーション能力がないほど低いと思っている人は間違いなく社交的な人を過大評価しています。
極端な話よくしゃべっているだけですごいと思ってしまうくらいに。
でも、実際は社交的と言われる人もできていないところがある、むしろコミュ障と言われる人の方が優位なところもあったりするのです。
意外と話を聞けていない人が多いという事実
あるアンケートで「あなたは人の話をちゃんと聞けていますか?」という質問を受けたとき、50%以上の人が「聞けている」と答えたそうです。
私自身、カウンセラーとして活動する中で「聞くこと」は基本中の基本なのですが、意外と難しくてできている人に会うことがほとんどありません。
その確率から考えても「50%以上はないだろうな」と思いました。
以前通っていた整骨院の先生とのやり取りですが、たいていの人はこんな感じのコミュニケーションを取っています。
私:「こないだ天橋立に行ったんですけど、あの辺りはめちゃくちゃ遠いですよね。」
相手:「あ~、天橋立って京都の北の方ですよね?実は私近くに住んでたことがありまして…そのとき付き合ってた彼女がね…(延々と続く)」
相手の話を自分の話にすり替える、話を聞けてない人にありがちなパターン。
私は心の中で「いやいや、あなたの彼女の話とか別に聞きたくないし」って思いながら聞いてました(笑)
よくしゃべる人ってこういう会話が多いんですよね。
「あなたは人の話をちゃんと聞けていますか?」という質問に対して、自信持って「聞けている」と言う人はたいてい聞けていない。
そもそも話を聞くことを軽視しているから「聞けている」と言えてしまう。
よくしゃべる社交的な人に多いのは、人間関係で悩むことがないからだと思います。
話が聞けるコミュニケーション上手を目指せばいい
人の話が聞けるコミュニケーション上手な人には以下のような特徴がみられます。
- 相手の話を途中で遮らずに最後まで聞ける「忍耐力」
- わからないことを正直に質問できる「素直さ」
- 話の背景を想像しながら聞ける「想像力」
- 相手の話が膨らみやすい質問ができる「質問力」
実は社交的な人より内向的な人の方が素質があったりするんですよね。
話を聞くしかできず我慢が習慣化しているから忍耐力があったり、マウントを取ろうとしても勝てないから素直に聞く感じになったり… 想像力や質問力は乏しい人が多いかもしれませんが。
どこができていて、どこができていないかも、自分のコミュニケーションを振り返って考えてみてください。
まずは「自分が話を聞けていない」ということに気付くこと、そして、それを認めることが人の話を聞けるようになるための第一ステップです。
「話し上手は聞き上手」と言われるように、聞き上手になれば、必然的に話し上手にもなれます。
相手の真意や意図を汲み取って話せるようになるから話し上手になるんですよね。
コミュニケーション能力が高まると必然的に人から好かれやすく尊敬されやすくなり、今まで嫌われていた同僚や低い評価を受けていた上司との関係を変えていくことだってできます。
ただ、表面だけ取り繕ってスキルであるように見せかけても何も変わりません。
自然とできるようになって初めて上手くいくようになります。
そのためには普段から聞くことを習慣化させて聞く力をつけたり、さらにその根本にある人間力を高めたりすることがどうしても必要となるのです。