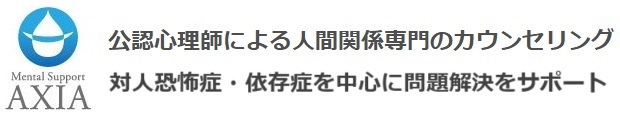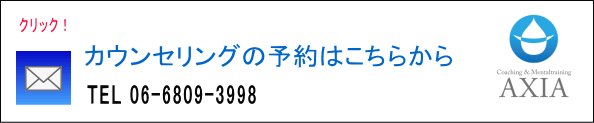自分が臭いのではないかと気にしすぎて、外出すら困難になっている方からのご相談があります。
自己臭恐怖症と呼ばれる症状で非常に深刻な悩みなのですが、カウンセリングを継続していただくことで改善に向かっていきます。
自己臭恐怖症とは
自己臭恐怖症は、自分の身体から発せられる口臭や体臭が非常に強いものだと思い込み、そのにおいのせいで「他人に迷惑を掛けて嫌われているのでは」と不安や恐怖を感じる症状です。
確信型対人恐怖症(思春期妄想症)の一種で、自臭症、自己臭症等と呼ばれることもあります。
もともと日本人はにおいに敏感なのですが、最近は「スメルハラスメント」という言葉が出てくるほど気にする人が増えています。
発汗や加齢などで強まる体臭。周囲に不快感を与える「スメルハラスメント(スメハラ)」の認知が進むにつれ、自分のにおいを気に病む「自己臭恐怖症」と診断される患者が増えている。
ほとんどが「幻臭」と呼ばれるものでにおいはしていないのですが、ワキガや口臭、ストレス臭、PATM等でにおいが発生しているケースもあります。
自己臭恐怖症になる原因と発症のキッカケ
自己臭恐怖症になる人は、生まれつき些細なことを気にしやすく、こだわりが強いところがあります。
そして、家庭環境や学校生活で自分を抑圧する習慣が形成され、自己肯定感が非常に低い状態になる。
傷つけられないよう必死に自分を守っている中で、以下のような出来事からにおいを気にしだして自己臭恐怖症を発症するのです。
- 家族や同級生に直接においのことを指摘された
- 自分のことをくさいと言われているように感じた
- 会話しているとき相手が鼻に手を当てた
- 同じ空間にいる人たちが咳払いをしやすいことに気付いた
- 車に同乗したときに窓を開けられた
エレベーター、職場、教室、車、バス、飛行機、電車等といった人が密集する空間や対面での会話等、においをかぎとられる状況に異常なほどの恐怖心を抱くため、必要以上に人とのかかわりを避ける傾向が見られます。
自分の体臭との関連付けと症状悪化
自己臭恐怖症で悩んでいる人は、鼻に手を当てた、鼻をすすった、咳をしたといった他人の行動を注意深く観察し、自分のにおいと結びつけては苦しんでいます。
自分の方を向いて話をしている人がいれば、自分のにおいのことを言っているとしか思えず、迷惑を掛けてしまっていることに罪悪感を抱く。
「くさい」という言葉に敏感になっているので、「くさい」と言われたと聞き間違って落ち込むこともあります。
客観的に見れば明らかに無関係なことまで自分のにおいと紐付けるようになっていくのです。
自己臭恐怖症になってしまうと「くさくない」「におっていない」と誰かに言ってもらえても、気を遣って嘘をついてくれているのではと思ったりでなかなか信用することができません。
においが電車の車両全体に広がる、学校中に広がるといった感覚になってくると、統合失調症の可能性が疑われます。
感情の抑圧がにおいを放っている感覚を生み出す
自己臭恐怖症で悩んでいる人は完璧主義で抱え込みやすい傾向が見られます。
他人に弱みを見せず一人で頑張って解決しようとする。 本当は「もう無理」となるはずが、我慢の習慣で感情がマヒしているから耐えることができてしまう。 胃潰瘍を繰り返したり、体に明らかな異変が起こっているのに自分が無理していることを自覚できない人もいました。
自覚できないうちに限界を超えてしまっていて、抑圧しきれずに漏れだした感情がにおいを放っているような感覚にさせる。
つまり、においというのは抑圧された感情であると言えます。
表現できていなかった感情を書き出す、カウンセリングで話すことによって改善した事例は数えきれないほどありました。
「どんな理由で良くなったと思いますか?」と尋ねたところ,「今まで人にいえなかったことを,レポートを書き始めてから,何か楽になったみたい」と答えた
引用元:治療的キーワード “悪い自分” を用いた口臭症 (自己臭恐怖症) の1治療経験例、1994、日本歯科心身医学会雑誌
また、理想化された完璧な自分と恥ずべき不完全な自分との狭間で、どちらにもなれないという葛藤も大きく影響しています。
対人恐怖症者について,極度に理想化された自己イメージである「理想自己」と,過度に矮小化された自己イメージである「恥ずべき自己」との二極を揺れ動き,決してその中間の自己イメージに安定することのないことを指摘している。彼らは「理想自己」の実現を希求しつつも,実際に「理想自己」が実現されそうになると,目立つことによって自分の存在が危うくなるのではないかという強い不安に襲われる。また逆に 「恥ずべき自己」にとどまることも彼らにとっては耐えられない苦痛である。人前でふるまうという「パフォーマンス状況」では,これら二極の葛藤が意識下のレベルで起こりやすいが,直接的に意識されるのは見られたくない自分の「漏れ出し」への恐れである。
『見られたくない自分の「漏れ出し」への恐れ』がにおいとして表出したと考えられるのです。
上手くいかないことをすべてにおいに結び付ける思い込み
自己臭恐怖症の特徴的な考え方として、うまくいかないことを何でもかんでも自分のにおいのせいにしていることがあります。
「人と仲良くなれない=自分が臭いからだ」 「職場でみんなの輪に入れない=自分が臭いからだ」 「あまり話しかけてもらえない=自分が臭いからだ」 という感じで、厳しい言い方をすると本質と向き合うことから逃げているわけです。
別に臭くても人と仲良くなれる人はいるし、話しかけてもらえる人だっています。
私が過去に在籍していた会社でオフィスに充満するほどきついワキガの人がいたのですが、多少は陰口を言われながらも周りとは仲良くできていました。
つまり、本当の原因はにおいではないのです。
でも、その原因と向き合うには怖すぎて、もしかすると自分の存在自体を脅かすものかもしれないと強烈な恐怖心を抱えているから、においのせいにしているほうが安全なんですよね。
この部分に少しずつ感覚的に気付いていくことができたときに、自己臭恐怖症克服への扉が開けます。
ず一っと考えたんですけど,私は人に良いふうに思ってほしくて,嫌われたくないからこんなになるんでしょうか?!誰にでも好かれたいと思って……。臭いで人に迷惑をかけてはいけないということにして,実は嫌われるのがこわいので”臭い”で逃げてる……ようで……何だかよく分かりません
引用元:治療的キーワード “悪い自分” を用いた口臭症 (自己臭恐怖症) の1治療経験例、1994、日本歯科心身医学会雑誌
根付いてしまった「自分が臭い」という強烈な思い込みから抜け出し、本当の問題に焦点を当てていけるかどうか。 そのためにも、においのこと以外に焦点を当てていくことが必要です。
日常生活で生じる症状ではなく、健康な部分に対して注意を向けたことにより、症状の低減を認識することができたと考えられよう。
においのこと以外に意識が向けば向くほどにおいへの意識が減少するので症状は緩和していきます。
自己臭恐怖症を克服するために
「におい」というのは人間である以上切り離せない要素です。
にもかかわらず、「におい」をなくそうとするのは自分の存在自体を否定することと同じ。
人間である以上なくせないはずのものをなくそうとして、においのある自分を否定し続けるから苦しみが生まれているのです。
他の対人関係では一切自己主張しない,いわば自分臭さを出さない存在である彼女にとって,思春期以降突出してきた自らの女性性,生命力といったものには戸惑いを感じ,目を背けがたいものとして拘り続けているのではないだろうか。
カウンセリングを受けながら、今までずっと消したいと目を背けてきた自分のにおいと向き合うことが本当の自分と向き合うこととなり、奥底に眠っている自分の存在意義、自分の本音に少しずつ気付けるようになっていく。
しかし、自分の本当の問題に気付くことで、失望、苦悩が頭をもたげて苦しむことにもなります。
「この前も少し話しましたが,自分がこんなに消極的で自信がない人聞だったなんて,ここ何週間で実感してしまって,かなり落ち込んでいます。課題(問題点)が取り除かれていくと本質(真の問題点)が残って,これって物理的なものじゃないから根が深くてかなり問題。これも一種の病気だと思うのですけど治るでしょうか」と書かれており,これまでの逃避的な対人関係の原因を,身体因から心理的因子に求めるような変化が起こったことが窺われた。
それでも、一緒に考えてくれるカウンセラーの支えのもと、どうすれば「においのある自分」で本音を表現して自分らしく生きていけるのか、よりよい人生を歩むことができるのかを真剣に考えて行動していくことによって自己臭恐怖症は克服できるのです。
「遅くまで開いているお店に入りました。この前と同様,もうあまり端の方とか,人が多いとかには,こだわらなくなりました。気にしなくなりました。ええいっ,もうどこでもイイヤ!!って感じです。移動の時は車だったのですが,車の中では隣の人と少し距離をとってましたが,前ほどのけぞるようなことはしなくなりました。その後,カラオケに行きましたが,なんだか今日はとても楽しく過ごしたように思います」
引用元:治療的キーワード “悪い自分” を用いた口臭症 (自己臭恐怖症) の1治療経験例、1994、日本歯科心身医学会雑誌
自己臭恐怖症の克服においてカウンセラーとの信頼関係構築は非常に重要です。
カウンセラーのプロフィールやブログを読んで慎重にご検討ください。
カウンセリングはオンラインで対応できないことはありませんが、基本的に直接お会いする対面をお願いしております。(遠方にお住まいの方の場合は初回だけ対面で二回目以降オンラインでの対応は可能です)