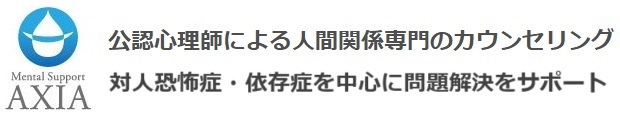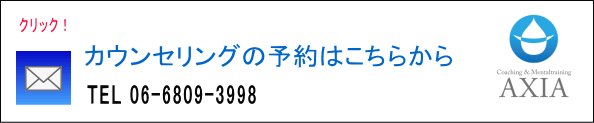1対1なら話せるのに3人以上の複数になった途端急に話せなくなる。
話したいけど話題についていけないし、何を話せばいいかわからない。話すことを思いついてもタイミングがつかめないから会話に入れない…
自信が持てず「変なこと言ってないか」「こんな話、誰も聞きたくないんじゃないか」とネガティブに考えてばかり。
自分以外の人たちが盛り上がっている中、一人だけ会話に入れず苦しんでいる人は少なくありません。
本記事では3人以上で話せなくなる原因と対処法、克服方法を詳しくお伝えしていきます。
3人以上の会話で話せなくなる3つの原因
話の展開についていけない「思考のタイムラグ」
3人以上のときは1対1に比べて話の展開が早くなりやすい傾向があります。
会話に参加する人数が増えれば増えるほど内容が表面的になりやすく、自分が話さなかったとしても他の人同士で話が進んでいきますからね。
その時々で思いついたことを話せばついていけるが、「何を話せばいいか」と考えているうちに遅れてしまう。
思考を挟むことでタイムラグが生じ、会話に入れなかったことを気にしてまた考えてを繰り返すことで話せない悪循環に陥っています。
結果として、話そうと思ったときには別の話題になっていて話せないということが起こってしまうのです。
「空気を読みすぎ」が生むHSP的な情報過多
3人以上になることで集団特有の「場の空気」が生まれます。
1対1なら相手に合わせるだけでよかったのが、場の空気まで読まないといけなくなる。
コミュニケーションは3人以上で一気に複雑化するのです。
相手の表情や雰囲気を気にしすぎて話すタイミングを失い、何か話さないとと焦って場違いな発言をしてしまう。
「空気が読めない自分は発達障害ではないか」と思う人は多いのですが、空気を読もうとし過ぎた結果なのでHSPに該当する人がほとんどです。
繊細さがあることで周りからの情報を過剰に受け取り、混乱してしまうことで話せなくなっています。
似通った特徴を持つHSPと発達障害。代表的な6つの特徴から違いを説明しています。
「自分が話さなくてもいい」という他人優先意識
1対1の会話とは違い3人以上の場合は自分が話さなくても成り立つので、話す必要性がない状況になります。
話すことが浮かんできたとしても、自分より他の人たちを優先する意識が働く。
他の人同士が話して楽しく過ごせるならそれでいい、変に自分が入って盛り下がるようなことはしたくないと思う。
自分よりも他人を優先しているから3人以上の場で話せなくなってしまうのです。
日常的に人の顔色をうかがい、気を遣っている人ほど話せない状態になる傾向が見られます。
人の顔色を窺ってしまう原因からどうすればやめることができるのかをお伝えしています。
3人以上の会話が苦手になってしまう心理的な背景
「嫌われたらどうしよう」という対人不安
「嫌われたらどうしよう」「変に思われたらどうしよう」といった不安が強い。
集団に上手く適応できないことで周りからコミュニケーションが取れない人間だと思われるのが怖い。
3人以上の場面で何かしらの不安や恐怖を感じていると言葉が出づらい状態になります。
人と会ったあと「楽しかった」よりも「疲れた」が上回る感覚になる人が多いですね。
嫌われないように、不快にさせないようにと過剰に気を遣い、普段から相手に合わせるコミュニケーションを取っている人は対人恐怖症に該当する状態かもしれません。
人が怖い、人と話すのが怖い。対人恐怖症の実態と克服方法をまとめました。
劣等感からくる「ダメな自分を知られたくない」意識
周りに比べて自分が劣っている、ダメだと思っていることで、自分と話してもつまらないのではないかと思っています。
だから、相手が自分と話しているときよりも他の人と話しているときの方が楽しそうに見えるのです。
ダメな自分を知られたくないからと隠そうとして話せることがなくなってしまう。
休日の過ごし方が話題になったとき、一人でアニメを見て過ごしていることを知られたくないと思っていたとすれば、自分に話を振られないようにと願いながら適当に相槌を打つだけになりますよね。
上手く誤魔化しているつもりでも周りは話したくなさそうな雰囲気を察して話を振らないようになっていく。
話を振ってもらえなくなったことを自分が嫌われているからだと思い込み、一人だけ馴染めていないことにさらなる劣等感を抱くのです。
集団コミュニケーションの土台となる父親との関係性
グループでの会話で失言をして全員から白い目で見られたとか、何かしらトラウマになるような経験があるわけではなく、昔から3人以上で話せなかったと言われるケースばかり。
なぜなのかと原因を掘り下げてみたところ、初めて三者関係が形成される父親とのコミュニケーションで問題を抱えていたことがわかりました。
集団との不適合感と父親との関係性は研究結果からも導き出されています。
注目すべきことは,日本人にあってはこうした集団への不適合感と「父親」との対話の有無が著しく関係していることである。(中略)日本人の場合,集団への適合という social skill は「父親」を媒介にして促進されるのではないかと考えられた。
人間は生まれてから母親との関係、1対1の関係を築きながら成長していきますが、次にかかわる2人目がたいていの場合父親になる。
父親との関係でつまずいたから3人以上で話すための土台が上手く形成されなかったという可能性が考えられるのです。
【即効性あり】3人以上の場で話せないときの対処法4選
信頼関係(ラポール)を築く「あいづち」への徹し方
3人以上の場であいづちだけでも気まずい思いをせず、楽しく輪に入って周りから仲間と認識されている人はいます。
今までそういう人を見たことはないでしょうか?
そもそも3人以上の会話では、意外とあいづちを打つことの方が大事だったりします。
会話参加者間の情報量が均等でなくてもラポールが生まれる。聞き手の役割を担い、あいづちを打つ人が存在することが重要なのである。まさに共話的な会話展開である。
※「ラポール」は信頼関係を意味する言葉です。
「うん、うん」「へー」「そうなんですね」「すごいですね」「わかります」「なるほど」等、相手の発言に対して何かしら返すようにしてみましょう。
私も飲み会ではたいてい聞き役であいづちを打っていることが多いですが、気まずい感じになったことはありません。
「あいづちだけでいい」と思うことは「話さないと」というプレッシャーを軽くしてくれるため、結果的に言葉が出やすくなる効果もあります。
会話を広げる「ど」から始まる質問テクニック
3人以上の会話に入るにあたって質問をすることは有効です。
「どう?」「どのように?」「どこ?」「どうして?」「どんな?」「どうやって?」「どれくらい?」等、「ど」から始まる質問は会話を広げてくれます。
「先週の日曜日に子どもの運動会があったんだ」と言われたら「どうでしたか?」と聞く。
「ディズニーランドの待ち時間がすごくて大変だったよ」と言われたら「どれくらい待ったんですか?」と聞く。
短い言葉で会話に入ることができるので周りのペースに遅れず参加しやすいです。
先程お伝えしたあいづちとセットでやっていただくとより会話がスムーズになります。
「話せない自分を受け入れる」開き直りの心理効果
3人以上で話せない自分が何かちょっと意識したところで劇的に話せるようにはなりません。
だから、「ここでは話せないよな」と話せない事実を受け入れるようにしてみましょう。
話せないからダメと思う必要はなく、ただこの状況では話せないと思うだけ。
「一対一なら話せるし、別にコミュニケーションは取れるから大丈夫だ」と思っておいてかまいません。
3人以上の場で話せない自分が話せないのは当然のこと。
「嫌だけど話せないんだから仕方ないじゃん」と自分に語り掛けてみるのもいいですね。
受け入れることができれば開き直ってきて緊張が緩和するため、結果的に話しやすい状態になることがあります。
周りに合わせすぎない「自分のスタイル」を貫く
話すペースがゆっくりの人もいれば速い人もいる。話すのが好きか話を聞くのが好きかも人によって違いますよね。
あとはリアクションが大きい小さいとか、身振り手振り使って話すかどうかとか…
3人以上の会話で困っていない人は自分のスタイルを崩さずに会話しています。
自分は気の利いた返しができるタイプじゃないと認識していれば、上手く返せなくても気にしないでしょう。
輪に入って話を聞ければ満足という人は聞き役で全然話さないけど、自分が話せていないことを気にしません。
普段1対1で話しているときを思い返して自分のスタイルで会話することを心がけてみてください。
周りに合わせよう合わせようとしすぎないことで結果的に話しやすい状態になります。
3人以上の場で話せるようになるための根本的な克服トレーニング
思考を挟まない「感覚で話す」反射的アウトプット訓練
3人以上で問題なく話せている人たちは感覚で話しています。
聞いた内容に対して話したいことや聞きたいことが反射的に湧き上がってくるからパッと言葉が出るのです。
一人のときに感じたことをリアルタイムで言葉にする習慣を持つようにしてみてください。
- ネコの動画を見て可愛いと思ったら「可愛い」と口に出す
- 乗り気でないことをしないといけないときに「あー、面倒くさいな」と言う
- ドラマで予想外の展開になったときに「え?なんで?」と言う
感じたことをすぐ口にすると思考を使いづらいため、感覚で話すトレーニングになります。
声に出せない場面では心の中で言う、スマホのメモに書くといったことで対応してみてください。
話題についていけるようにする「興味関心の幅」の広げ方
3人以上の会話では自分が知らない話題を他の人同士が話す場面が必ず出てきます。
自分が見たことのないドラマのこと、他の人同士で遊びに行ったときのこと、自分が関心のないスポーツのこと等。
知らないことが多ければ多いほど会話に入りづらくなってしまうので、事前にある程度の情報を得ておくことが必要なのです。
まずSNSやニュース、YouTube等でいろんなジャンルの情報に触れる機会を増やしていきましょう。
そして、思ったことや感じたことをスマホのメモに書き出してみる。
ヤフーニュースやYouTube、掲示板にコメントを書くこともできればやってみてください。
興味が持てないジャンルを無理やり見ていても情報が入ってきませんので、自分が興味のある範囲から少しずつ広げていく形が良いのではと思っています。
言葉を出やすくさせる言語化習慣
普段から言語化する機会が多ければ多いほど3人以上の場でも自然と言葉が出てきやすくなります。
よくしゃべる人は言語化する機会が多いから話が止まらないわけです。
以下のような形で日々自分の思いや考えを振り返って言語化するようにしてみましょう。
- 最近観た動画がすごく面白かった
- 飲食店の接客が悪くて嫌な思いをした
- 旅行した話を聞いて自分も行ってみたいと思った
- 出費がかさんできたので節約しないとと思った
一日の終わりにノートに書き出してみるのがいいですね。
Xで趣味のアカウントを作ってポスト、リプライをしていくのも練習になります。
一人で悩まないために:専門家によるカウンセリングを活用する
カウンセリングでは詳しい内容をお聴きした上でアドバイスをおこない、3人以上の場で言葉が出やすい状態にしていきます。
- 話したいことはあるのにタイミングがつかめない
- 相槌だけでいいと頭ではわかっているけどソワソワしてしまう
- どうしても周りにどう思われているかが気になる
自分なりに頑張って改善しようとしているけどなかなか変わらないという場合は、一度カウンセリングを受けてみてください。
3人以上の場で話せない状態は原因に気付き、根本的な問題を解決することによって克服できるものです。
一人で悩んでいると悪化していくことがありますので、なるべく早い段階でご相談いただければと思っております。