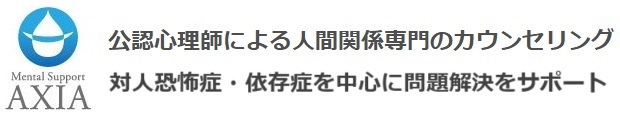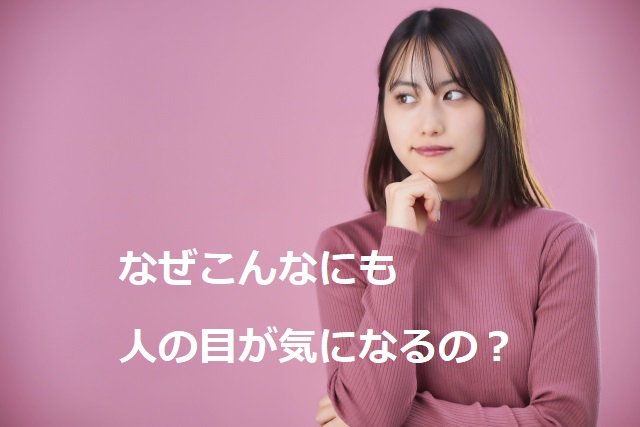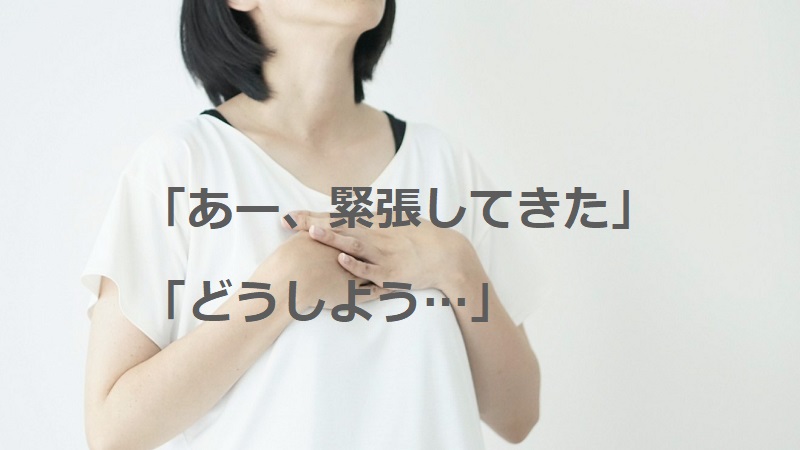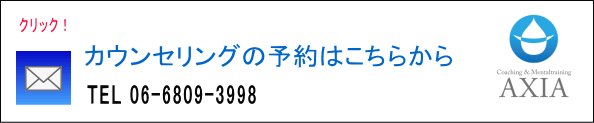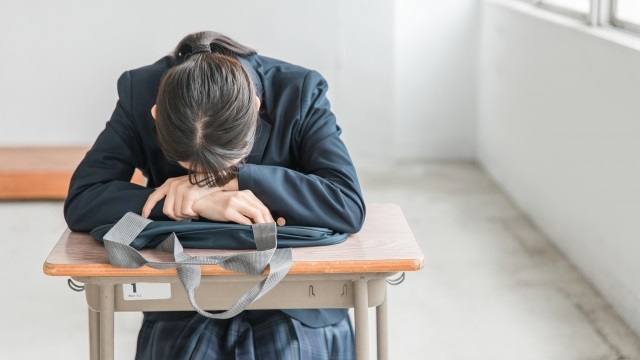集中して授業を受けることができず内容がまったく頭に入ってこない。
日中はデスクワークがほとんどできずいつも残業して何とか終わらせている。
視界に入った人が気になって目の前のことに集中できない状態では学校や職場で支障をきたすから大変です。
なぜ人が視界に入ると集中できなくなるのか、どうすれば改善できるのかについてお伝えしていきます。
人が視界に入ると集中できなくなってしまう原因
生まれ持った性質による二次障害
いずれかの性質を持っている人は、診断が下りないグレーゾーンも含め、二次障害として視界に入った人が気になる問題が起こりやすい傾向が見られます。
HSPは人の気持ちに敏感であるがゆえ、他人の些細な反応にも気付いて意識が向いてしまう。
ADHDは注意力が散漫で目の前のことに集中しづらいから視界に入った人に意識が向きやすい。
単純にHSPかADHDであれば視界に入った人が気になってしまうとは言えませんが、今までのカウンセリング事例からも関連が深いことが証明されています。
似通った特徴を持つHSPと発達障害。代表的な6つの特徴から違いを説明しています。
他者からの評価への依存
視界に入った人が気になる原因として「他人が自分をどう見ているか」という他人からの評価への依存があります。
相手に嫌われたくない気持ちが強いから相手にどう思われているかが気になって意識してしまう。意識することで相手に嫌がられるのはわかっているけど気になって仕方がないからどうしても意識してしまう。
自信がなくて他人の反応にビクビク、オドオドしている状態をイメージしていただければわかりやすいかと思います。
自分で考えて実行すること、結果を出すためにどうすればいいかを考えながら試行錯誤し続けること、自分の感情を上手くコントロールすること等の経験が少ないため、他人の評価に依存せざるを得ない状態になっているのです。
自分のことを自分でコントロールできる感覚がないから、視線もコントロールできず見てしまう側面があります。
人の視線が怖いと感じる他者視線恐怖症の改善方法をお伝えしています。
怒りの感情の抑圧
例えば、凶器を持っているとか奇声を発しているとか、明らかに危険だとわかる人がいたら誰でも警戒して意識を向けますよね。
視界に入った人に意識が向いてしまうのは警戒心の表れであり、まるで相手を危険人物であるかのように見ている状態だと言えます。
なぜ他人を危険人物のように見てしまうのでしょうか?
それは「投影」と呼ばれる心理現象によって自分の不満や怒りが他人に映し出されているからです。
不満や怒りを抑圧している人ほど他人に恐怖を感じやすく、視界に入った人に意識を向けざるをえない状態になっています。
相手が怒っている、自分を嫌っていると思い込んで苦しむ心理についてお伝えしています。
人が視界に入っても目の前のことに集中しやすくするための対処法
自分が集中しやすい本来の体勢に戻す
「どうすれば人を視界に入れないようにできるか」と考え、対策を打っている人がほとんどです。
職場であればパソコンの向きを調整したり、座る位置や体の向きを変えてみたり。
集中できないと仕事が進まないから必死にやります。
しかし、人を視界に入れないようにするほど不自然な体勢になるから集中しづらくなってしまう。
集中できるようになるためには、自分が集中しやすい体勢にすることが必要なのです。
「本来の自分の体勢はどんな感じだったのか?自分はどういう状態なら集中しやすいのか?」を考えた上で少しでも近づけてみてください。
実際に体勢を変えたら集中しやすくなったと言う人は何人もいました。
視界に入った人がどうしても気になってしまうので、なかなか難しいとは思いますができる範囲でやっていただければと思います。
緊張を緩和させる
人が視界に入って集中できないときはものすごく緊張しています。
緊張状態だから周りの些細な反応にも過敏に反応、注視する視線の向け方になってしまうのです。
人はリラックスしているときに自然と集中します。
だから、「目の前のことに集中しよう」と意識を強めるのではなく、リラックスで集中できる状態を作ることが効果的です。
呼吸法が有効なのですが、一般的な腹式呼吸ではなかなか深い呼吸ができずリラックスできません。
まず横隔膜に動きを出すことが必要となるため、胸式呼吸から取り組んでみてください。
胸に手を当てた状態で息を吸ったときに膨らむ、吐いたときにへこむを5回、寝る前の時間にやってみましょう。
ある程度深い呼吸ができてきた段階で胸式呼吸のあとに腹式呼吸を5回していきます。
感覚が掴めてきたら人が視界に入って集中できない場面でも、呼吸を深めてリラックス状態を作ることができるようになります。
面接やプレゼン、朝のスピーチ等、人前で話す場面で緊張しないために有効な方法をお伝えしています。緊張をほぐす応急処置は日常生活でも活用していただけます。
人が視界に入ると集中できない状態を改善するために
自分の状態を理解して上手く付き合っていく
HSPや発達障害に該当する状態であれば、周りの情報に反応してしまいやすいのはあります。
また、該当しない場合でも反応しやすい状態になっている可能性は高いため、感情や欲求、ストレスの観点から自分を見ていくことが必要です。
不安が強い、承認欲求が強い、ストレスが過度にかかっている。
どれか一つだけで十分過敏になりますが、複数重なればより過敏さは増してしまいます。
視界に入った人に反応してしまう要素は何なのかを一度考えてみてください。
カウンセリングでは幼少期のエピソードをもとに、生まれ持った性質、家庭や学校で形成された習慣等を紐解き、自分の状態を知るサポートをおこないます。
抑え込んできた自分の気持ちに気付く
親子関係や学校生活等でずっと我慢してきたことはありませんか?
人が視界に入ると集中できない状態の人は、相手に迷惑をかけないことが最重要になっているため、相手優先で自分を蔑ろにしてしまっていることが多いです。
まずは日々の生活で自分の感情の動きに目を向けてみるようにしてみてください。
相手を優先することで自分が嫌な気持ちになっていないかどうか、不満に思うことがないか、イラッとすることがないか…
今まで抑え続けてきた影響で感じづらくなっているので、「ちょっと嫌かもしれない」くらいのことから拾っていくのがいいと思います。
自分の気持ちがわかってくることで自分を大事にしようとする意識が芽生え、心に余裕が出てくることによって人が視界に入っても反応しない状態になるのです。
カウンセリングでは自覚しづらい感情に焦点が当たるようにサポートしていきます。
視線のことが気になりながらも人とのかかわりを持つ
「自分が視界に入れたら相手が嫌な思いをするに違いない」という自分の考えで相手を見ているから、相手も自分と同じくらい視線に対して過敏だと思ってしまう。
「でも、実際は気にしない人もいるわけだし相手によって変わるはず」と頭では理解していても感覚的に理解できていないからどうしてもそう考えてしまいます。
自分が視界に入れることで迷惑を掛けてしまうから人とのかかわりを避ける。
避けることによってどんどん自分の考えに固執する。
自分の考えに固執することによって自分が視線を気にするのと同じくらい他人も視線を気にすると思い込んでしまう。
余計に意識が向いて迷惑を掛けてしまうことを気にして人とかかわれなくなる。
この悪循環から抜け出すために人とのかかわりが必須となるのです。
他人の思いや考え、価値観に触れていく中で自他の線引きができ、視界に入った人を感覚的に切り離せる状態になります。
人が視界に入ると集中できない状態で日々しんどい思いをしておられるようでしたらご相談ください。