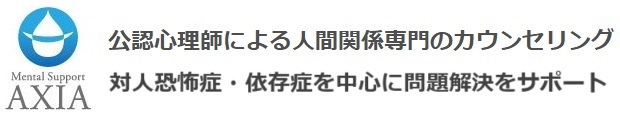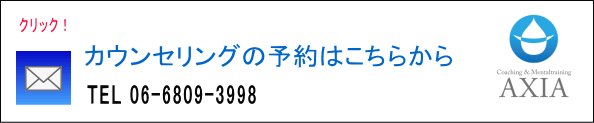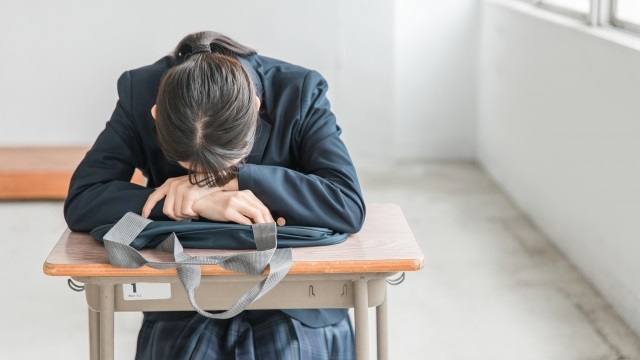「脇見恐怖症で人を見てしまうのがやめられない」「自分の視線で不快な思いをさせているのではないか」とお悩みの方へ。
私はカウンセラーとして活動を始めた当初から、脇見恐怖症と呼ばれる症状のご相談を数多く受けてきました。
脇見恐怖症は期間の経過と共に悪化しやすい厄介な症状ですが、カウンセリングで取り組みを続けることによって克服へと向かいます。
本記事では、脇見恐怖症がなぜ起こるのかという根本原因(過敏さ、目の使い方、認知の歪み等)を深く掘り下げるとともに、あなたが抱える不安や恐怖を改善し、精神的な自立へと向かうためのカウンセリングの具体的なプロセスをお伝えします。
症状をなくすことではなく自分らしい生き方を取り戻すために。
脇見恐怖症の悩みを抱えている方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。
脇見恐怖症とは?:視線への不安、恐怖、罪悪感を抱く症状
脇見恐怖症は、自分の視界に入ってくる人を意識することがやめられず、相手に不快な思いをさせてしまうことに不安や恐怖、罪悪感を抱く症状が代表的です。
「視界に入った人に意識を向ける=見ている」という感覚になり、視界に入っている人がソワソワしている、咳払いをする、別の場所へ移動する、関係がギクシャクする等があれば、自分が見てしまったせいだと思って苦しみます。
執着心、他者への依存心が非常に強く、劣等感や無価値感を抱えている人が多いです。
脇見恐怖症は正式な診断名ではないため、精神障害の診断基準として用いられるDSM-5、ICD-10には記載がありません。
対人恐怖症に分類される視線恐怖症の一種と言われますが、実際に対応してきた中で「一概に視線恐怖症とは言えない」というのが私の見解です。
脇見恐怖症で日常生活に支障をきたす具体的な症状事例
脇見恐怖症の症状として以下のような事例があります。
- 人とすれ違うのが怖くて日中に出歩くことができない
- 授業中に顔を上げることができず黒板を見ることができない
- 隣の席にいる人が気になって試験の問題を解くことができない
- 向かい側の席にいる人が視界に入るとパソコンでの仕事ができない
- 電車やバスで顔を上げることができず目を閉じてやり過ごす
- 顔を上げるたび必ず誰かと目が合う
- カフェやファミレス等の視界に人が入る席に座れない
- 異性に気があると勘違いされて困る
- 家族と一緒にテレビを見るのが苦痛
脇見恐怖症の実態:「実際は見ている」感覚と「見ていない」現実
本人の中では実際に見ている感覚になっているケースがほとんどで、インターネットやSNS上では「見ている」と表現する人は多いですが、今までのご相談事例から相手が気付くほど見ている人は少ない印象です。
見るとしても確認程度にチラッと見るか、「脇見」という名前の通り横目で少し見るくらい。
自分の姿をスマホの動画で撮影したら見ていなかった、脇見恐怖症の人同士が集まるオフ会で確認し合ったら実際は見ていなかったという話はよく聞きます。
電波を飛ばしている等といった発言が出ることから統合失調症の可能性も考えられますが、どちらかといえば確証バイアスと呼ばれる思考の偏りによるものです。
自分の視線で相手を不快にさせないかどうかを気にしすぎるあまり、視界に入れただけで見ているような感覚になってしまうのではないかと思っています。
見てはいけないと思うのに見てしまう症状も脇見恐怖症に含まれる
人を見ることがやめられず、不快な思いをさせてしまうことに罪悪感を抱くのは自己視線恐怖症の症状です。
しかし、過去の文献で以下のような脇見恐怖症の症状が自己視線恐怖症として扱われています。
〔症例2〕TM 男性,発症:18歳,自己視線恐怖
高卒後,予備校に通っていたとき,教室などで無意識のうちに自分が人を見てしまうことがよくあった。すると,自分の視線に気づいた人が不愉快になるようでチラと見返してくるので,それが苦痛に感じられた。現在,授業中は教室の右端に座り,左手で左目をさえぎるようにしてノートをとっているので,あまり気にならない。他の人は視野の周辺に意識があまり向かないようだが,自分は隣の人が気になる。
実際に道行く人と何度も目が合ってしまう、学校や職場で見ていることを指摘された等の話も聞きますので、見てはいけないと思うのに見てしまう症状も脇見恐怖症に含まれると考えられます。
脇見恐怖症の根本原因:なぜ視線が気になりやめられないのか?
些細なことに反応しやすい過敏さ
何かしらの理由で過敏さを抱えていることは影響します。
自分の視線がどうなのか、他人の反応がどうなのか、自分がどう思われているのか等、過敏さがあるから些細なことが気になりやすく、気になったらそのことばかりにとらわれやすいのです。
脇見恐怖症という悩みを抱えることで生じるストレスがさらに過敏さを強化し、悪化していく傾向が見られます。
目の使い方の問題
本来人の視線は焦点を当てる見方が5~10%、焦点を当てず周辺視野を使う見方が90%以上と言われます。
視界に入った人が見えるのは当然のことですが、この「見える」は周辺視野を使った見方。
しかし、脇見恐怖症の感覚では「見ている」になっていることから、焦点を当てる見方になっているわけです。
目の使い方の問題は、触覚、前庭覚(平衡感覚や重力感)、固有感覚(身体の動きに関する感覚)を中心とする感覚が上手く統合されていないことによって起こります。
感情や欲求の抑圧
不安や恐怖、怒り等の感情によって警戒心が高まり、視界に入る人に意識を向けざるを得ない、見ずにいられない状態になっている。
自分の視線で他人をコントロールできる感覚は支配欲求によるもの。
脇見恐怖症という症状を抱える自分に特別感を見いだすのは承認欲求が影響しているため、歪んだ形で欲求を満たそうとしている面があります。
しかし、感情や欲求を抑圧していることで自覚できず、なぜか人が気になってしまう、見てしまうという感覚になっているのです。
自分が我慢して丸く収まるならいいと思っていませんか?感情の抑圧は自覚がないまま大きな問題を引き起こしています。
認知の歪み
べき思考や白黒思考、完璧主義といった認知の歪みが影響しています。
人は生活をしていく以上、多少なり迷惑を掛けているものですが、「人に迷惑を掛けてはならない」という考えでいるとそれが許せなくなりますよね。
自分に対しても「こうあるべきだ」という考えを押し付け、理想とかけ離れた自分はダメだと思う。
認知の歪みによって自分のことが許せない、受け入れられない状態になっていることが脇見恐怖症につながっているのです。
「自分を受け入れる」ということ、そして、自分を受け入れるためにどうすればいいかについてお伝えしております。
アイデンティティの未確立
自我(アイデンティティ)が確立されていないことによって、自分と他人の境界線を引くことができず一体化。
自分が気になることは他人も気になるとしか思えない感覚が脇見恐怖症を引き起こす要因になるのです。
自分自身と向き合って可能性を切り捨てないといけないタイミングで目を背けた結果、自我が確立できないままの状態になっている。
自我が曖昧な思春期に脇見恐怖症を発症しやすい傾向からも関連性があると言えます。
他人や環境等、自分以外のことに責任転嫁してきた傾向が強い人ほど、アイデンティティの問題が影響している可能性が高いです。
悪化のサイクル:脇見恐怖症をさらに強めてしまう2つの意識
「見てはいけない」という意識
脇見恐怖症で悩んでいる人は、他人に迷惑を掛けている感覚があるため、常に他人の反応を拾っています。
そして、「また脇見で迷惑を掛けてしまった」と思い、罪悪感に苛まれて苦しむ。
自分は相手に配慮して見ないようにしているはずが見てしまい、相手に嫌がらせをするような人と誤解されていることに傷付く。
繰り返していくうちに「見てはいけない」という意識はどんどん強まっていきます。
「見てはいけない」と思えば思うほど症状を意識することになってしまい、結果として脇見恐怖症が悪化していくのです。
女性の胸以外に太もも、男性の股間や薄くなった頭髪等を見てしまうことがやめられず困っている人もいます。どちらかというと女性からのご相談が多い内容です。
症状をなくそうとする意識
脇見恐怖症を発症すると人に迷惑を掛けてしまうだけでなく、日々の生活に支障をきたすようになります。
- 症状のせいで嫌われるから友達ができない
- 症状のせいで黒板が見れないから授業が受けられない
- 症状のせいで集中できないから仕事が手につかない
症状によって困ることが多いので「この症状さえなければ」と思うようになり、症状をなくそうとすることでとらわれていきます。
症状のことばかり考えて過ごす日々で自分にとって大切なことを見失い、人生が空洞化していくことで抱える虚しさを誤魔化すため症状に固執する。
症状をなくそうとする意識が脇見恐怖症を悪化させているところがあるのです。
対人恐怖症で悩んでいる人が持つ症状をなくすことへの囚われ。どうすれば抜け出すことができるのかを書いています。
脇見恐怖症を克服し改善へ導くカウンセリングの取り組み
そもそも脇見恐怖症の概念が曖昧で明確な定義がない以上、克服プログラムのようなものを作成することはできません。
対人恐怖症、思春期妄想症、強迫性障害、統合失調症、パーソナリティ障害、愛着障害、発達障害、HSP等の可能性を踏まえ、個別に対応していくことが必要です。
実際にどういう取り組みをしていくかは人によって異なりますが、下記のような方向性でカウンセリングをおこなっております。
【カウンセリングの方向性1】脇見恐怖症の悩みと距離を置き客観視する
脇見恐怖症という悩みを抱えることによって、どうすれば克服できるのかばかり考えるようになる。
悩みと一体化してしまうことで客観視できなくなり、どんどん悩みに飲み込まれていく状態になっています。
一旦悩みから離れることができれば、少し距離を置いて悩みに対処することができるようになり、克服しやすい状態になります。
悩みを解消したいと思うのは当然ですが、思いながらも脇見恐怖症のことばかり考えないことが大切なのです。
【カウンセリングの方向性2】自己を制御する感覚(制御感)を養う
自分が自分を制御できない状態に陥っているから、他人に意識を向けたくないのに向けてしまう、見たくないのに見てしまうといった症状が出ています。
カウンセリングで自分の性質、感情や欲求等と向き合い、なぜ自分を制御できない状態になっているのかを知る。
その上で自分を制御する感覚を養う取り組みをおこなっていきます。
そもそも感情や欲求を制御する力が弱いのか、抑圧の習慣で衝動が強まってしまっているのか等、人によって原因は異なりますが、継続していく中で制御感を養うことは可能です。
【カウンセリングの方向性3】症状のある自分を受け入れ統合する
症状がある自分はおかしい、変だと思うことで否定している。
どこか症状を抱えている自分は自分ではなく、症状をなくすことで本当の自分になれると思っているところがあります。
しかし、光があるところに必ず影ができるのと同じく、人間の心にも光と影があり、症状を含めた自分の影をなくそうとしているから苦しいのです。
症状のある自分、自分の影を認めることができるように働きかけていきます。
【カウンセリングの方向性4】視線を「見てしまう(do)」から「見える(be)」へ変える
他人に意識を向けてしまう、見てしまう(do)を、他人が視界に入る、見える(be)に変えていくことが必要です。
意識的に見るのではなく、ただ視界に入るだけの感覚になれば、罪悪感に苛まれることも不安や恐怖に怯えることもなくなります。
相手を見ることを必要とする心理状態が背景にあるのですが、カウンセリングで改善していくことが可能です。
本来の視線の向け方がわからなくなっている人が多いため、具体的なレクチャーも交えてアドバイスしております。
【カウンセリングの方向性5】他人依存から精神的に自立する
脇見をして相手が反応するから見ないようにする、人に変に思われそうだから言わない、症状が出るからなるべく外に出ない、症状の改善につながるかわからないからやらない…
常に自分ではなく他人や症状が「主」になり、自分が「従」の依存的な状態になっています。
相手がどう思おうが自分がやりたいからやる、周りにどう思われようが自分が嫌だからやらない、症状でしんどいけど自分がやりたいからやる、症状の改善につながるかわからないけど自分が成長できるからやる。
自分で考えて動ける自分を「主」にした自由な感覚、精神的自立に向かうほど脇見恐怖症は改善していきます。
【カウンセリングの方向性6】症状の必要性をなくし根本から克服する
脇見恐怖症という症状が出ているのは今の自分にとって必要だから。
アドラー心理学や神経症の理論が有名ですが、症状は何かしらの目的を果たすために存在していると言われます。
症状が必要な状態である限りなくすことができないため、必要でない状態を目指すのが脇見恐怖症の克服につながるのです。
カウンセリングで自分自身と向き合い、症状の必要性に気付いていく中で何をすればいいかがわかってきます。
脇見恐怖症は一人で抱え込まず専門的なカウンセリングを受けることで克服に向かうものです。
当カウンセリングルームは脇見恐怖症の克服をサポートしてきた実績が数多くあります。
視界に入った人を意識することがやめられない、どうしても見てしまうといったことでお悩みでしたらご相談ください。
- 初めてのカウンセリングを検討中の方へ
- カウンセラーの選び方
- カウンセリングに依存してしまうのが不安な方へ
- カウンセリングの終結
- 担当カウンセラー紹介
- カウンセリングのメニュー・料金
- カウンセリングルームへのアクセス
- カウンセリングを受けられた方のご感想
- カウンセリングの予約方法